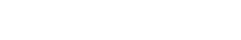賃貸物件に保証人は不要?そのメリット・デメリットや審査のコツまで解説!
- 2025.09.14
- 家賃保証料

「保証人を頼める人がいない…」
「親が高齢で、保証人をお願いするのは気が引ける…」
賃貸物件を探す際、多くの方が直面するのが「保証人」の問題です。保証人がいないという理由で、お部屋探しを諦めかけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、保証人がいなくても賃貸物件を借りることは十分に可能です。
この記事では、なぜ保証人なしで賃貸契約ができるのか、その具体的な仕組みから、メリット・デメリット、そして気になる審査を通過するためのポイントまで徹底的に解説していきます。
この記事を読めば、保証人不要物件に関する正しい知識を身につけ、お得に新しい住まいを見つけるための一歩を踏み出せるはずです。ぜひ参考にしてください。
保証人なしでも賃貸は借りられる!

近年「保証人不要」を掲げる賃貸マンションやアパートが非常に多くなりました。実際に、令和3年の国土交通省の調査では、家賃保証会社を利用して契約されたケースが全体の約8割を占めており、保証人なしで借りるのが当たり前の時代になっています。
ここでは、保証人不要の背景と基本的な仕組みについて理解を深めましょう。
参考:国土交通省「賃貸住宅を借りたい人へ—家賃債務保証で安心に」
保証人不要=家賃保証会社の利用が一般的
現在の賃貸業界で「保証人不要」とされている物件は、「誰でも無条件で借りられる」という意味ではありません。その多くは、「連帯保証人の代わりに、家賃保証会社を利用することが必須」という条件になっています。
家賃保証会社とは、万が一家賃の滞納があった場合に、一時的に家賃を立て替えて大家さん(貸主)に支払ってくれる会社のことです。入居者(借主)は、そのサービスを利用するための「保証料」を支払うことで、保証人がいなくても賃貸契約を結ぶことが可能になります。
保証会社のシステムには主に2つのタイプがあります。
- 一般保証型:借主が家賃を滞納した際に保証会社が貸主に立て替え、後日借主に請求
- 支払委託型:借主が保証会社に家賃を支払い、保証会社が貸主に送金する
このシステムにより、貸主は家賃滞納リスクを軽減でき、借主は保証人を探す手間が省けるため、双方にメリットがある仕組みとして急速に普及しました。
そもそも「保証人」や「連帯保証人」とは?役割と違い
これまで一般的だった「保証人」と「連帯保証人」は、その役割と責任の重さが大きく異なります。
| 項目 | 内容 |
| 保証人 | 借主が家賃を支払えなくなった際、最終的な支払い義務を負う。貸主はまず借主本人に請求し、それでも回収できない場合に初めて保証人に請求ができる。 |
| 連帯保証人 | 借主とほぼ「同等の重い責任」を負う。貸主は、借主の支払い能力に関わらず、いきなり連帯保証人に対して家賃の支払いを請求することも可能。賃貸契約では、こちらの「連帯保証人」を求められるケースがほとんどだった。 |
| 家賃保証会社 | 連帯保証人の役割を法人として代行するサービス。入居者は保証料を支払うことで、親族や知人に重い責任を負わせることなく、部屋を借りることができる。 |
保証人の場合、借主が支払わない状況でも「まず借主に請求してください」と主張できる権利(催告の抗弁権)や、借主に財産がある場合は「借主の財産から回収してください」と主張できる権利(検索の抗弁権)があります。
一方、連帯保証人はこれらの権利がなく、貸主から請求されれば借主と同等の責任を負わなければなりません。つまり、連帯保証人は借主と同じ立場で支払い義務を負うため、より重い責任を背負うことになります。
保証人不要の賃貸物件が増えている理由
保証人不要の賃貸物件が増加している背景には、複数の社会的要因があります。
第一に、少子高齢化により保証人を頼める親族が減少していることが挙げられます。核家族化や人間関係の希薄化により、従来のような身内に頼る保証人制度が機能しにくくなってきています。
第二に、2020年の民法改正が大きな転換点となりました。連帯保証人に極度額の設定が義務化されたことで、保証人を引き受けることのリスクが明確化され、保証人探しがより困難になったのです。
第三に、家賃保証会社の市場拡大があります。ある調査によると、2024年度の家賃債務保証市場規模は2,548億円に達し、前年度比106.7%の成長を記録しています。
このような背景から、貸主側も保証人に頼るよりも、確実性の高い保証会社を利用する方向にシフトしており、結果として保証人不要の物件が増加しているのです。
参考:株式会社矢野経済研究所「家賃債務保証市場規模は2029年度には3,500億円を超える水準まで拡大を予測~事業用家賃債務保証の拡大~」
保証人不要で賃貸を借りる良し悪し
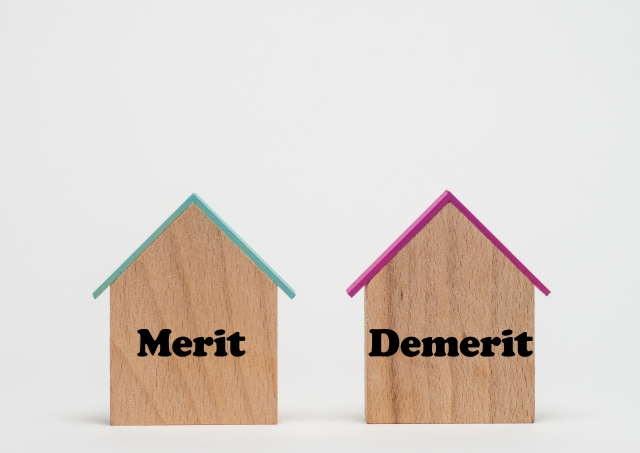
家賃保証会社を利用することで、保証人がいないという悩みを解決できますが、もちろん良い点ばかりではありません。
メリットとデメリットの両方をしっかり把握し、納得のいくお部屋探しをしましょう。
【メリット】親族や知人に頼らずスピーディーに契約できる
| ・両親や親戚に負担をかけない ・契約手続きが早い ・フリーランスや学生、外国籍の人でも契約しやすい |
保証人不要物件の最大のメリットは、親族や知人に迷惑をかけることなく、迅速に契約手続きを進められることです。
従来の保証人制度では、保証人候補者への説明や承諾書の取得、必要書類の準備など、多くの時間と手間がかかりました。また、保証人を引き受けてもらうことで人間関係に負担をかける心配も。
家賃保証会社を利用すれば、これらの煩雑な手続きが不要となり、申込みから契約まで1週間以内に完了することも可能です。特に転勤や進学などで急いで住居を確保したい場合、この迅速性は大きなメリットとなるでしょう。
さらに、保証人を頼める人がいない単身者や、親族が高齢で保証能力に不安がある場合でも、安心して賃貸契約を結ぶことができます。
【デメリット】保証料や更新料が発生!物件が限られる場合も
| ・初回家賃保証料や更新料がかかる ・物件が制限される ・審査基準の厳格化 |
一方のデメリットは、金銭的な負担が発生することです。家賃保証会社を利用する際には、初期費用として「初回家賃保証料」を支払う必要があります。金額の相場は家賃の0.5ヶ月~1ヶ月分、もしくは数万円の定額制など、会社によってさまざまです。
たとえば、家賃が8万円の一人暮らしの賃貸マンションを契約すると、初期家賃保証料は4万〜8万円。これに敷金・礼金・仲介手数料を加えると、初期費用だけで40万円以上になるケースも珍しくありません。
さらに、1年または2年ごとに「更新料」として1万~2万円程度の支払いが必要になるケースがほとんどです。長期間住む場合は相当な負担になってくるでしょう。
また、すべての賃貸物件が保証人不要というわけではありません。希望の間取りや理想の家を見つけても、その物件では保証会社を利用できないケースもあります。特に新築マンションや人気エリアの物件では、連帯保証人を求められる場合もあります。
保証人不要物件の審査は厳しい?

保証人が不要な分、入居希望者本人に安定した支払い能力があるかどうかが厳しく審査されます。しかし、事前にポイントを押さえておけば、通過率は十分に高められます。
保証人不要物件の審査基準
保証会社の審査は、主に申込書に記載された「属性情報」と、過去の支払い履歴である「信用情報」の2つの軸で判断されます。
- 属性情報:安定した支払い能力があるかどうか。特に「収入(家賃の3~4倍の月収が目安)」「雇用形態」「勤続年数」が重要なポイントとされる
- 信用情報:過去の家賃滞納歴やクレジットカード、ローンの延滞履歴をチェック。特に信用系保証会社では、個人信用情報機関(CIC、JICC等)のデータを参照するため、金融事故があると審査が厳しくなる傾向
東京大学の研究によると、20歳未満の場合は通過率が約31%低下し、60歳以上の高齢者でも通過率が下がるといった結果も出ています。
参考:東京大学空間情報科学研究センター「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」
通過率を上げる方法
審査の通過率を上げるためには、事前準備と丁寧な対応が重要です。
まず、収入証明書類を準備しておくとよいでしょう。申込時に必須でなくても、後から提出を求められるケースは多いです。源泉徴収票や確定申告書などをあらかじめ用意しておくと、審査がスムーズに進みます。
正社員以外の方は、直近3か月分の通帳コピーや取引先との契約書など、安定収入を示す資料を複数準備すると有利になります。
また、内見を終えて入居の意思が固まったら、申込書は正確・丁寧を心がけて記載しましょう。勤務先は略さず正式名称で書く、空欄を作らないなど、丁寧な書類作成が大切です。雑な書類は心証を悪くする可能性があります。
もし収入面や信用情報に不安がある場合は、隠さずに不動産会社の担当者に相談することも大切です。状況に応じた最適な保証会社を提案してくれるなど、プロとして力を貸してくれる可能性があります。
審査に通らないときの対処法
もし初回の審査で落ちてしまった場合でも、諦める必要はありません。
まず、別の保証会社での再審査を検討しましょう。保証会社によって審査基準が異なるため、A社で落ちてもB社では通るケースもあります。
次に、家賃を下げることも検討してみてください。同じエリアでも駅からの距離が少し遠い物件や、築が経っている一戸建てやマンションであれば、家賃が安く設定されているため審査に通る可能性があります。
それでも難しい場合は、保証人不要という条件に固執せず、親族に相談して連帯保証人になってもらうか、UR賃貸住宅など保証人が原則不要な物件も視野に入れてお部屋を探すのがよいでしょう。
保証人不要物件の市場動向と展望

近年、保証人不要の物件が急速に増えている大きな理由のひとつに、2020年4月1日に施行された民法改正があります。この法改正は、私たちの賃貸契約に大きな影響を与えました。
これまで、個人が連帯保証人になる場合、その責任の範囲が非常に曖昧でした。しかし、民法改正によって、貸主は連帯保証人と契約する際に「極度額」という、保証する金額の上限を必ず書面で定めなければならなくなったのです。
たとえば、「極度額100万円」と設定されれば、連帯保証人が負う責任は最大でも100万円までとなります。これにより保証人の責任範囲は明確化されましたが、同時に「こんなに高額な責任を負うのか」という心理的なハードルが上がり、以前にも増して個人に連帯保証人を依頼しにくくなりました。
この法改正が、結果的に貸主側にとっても借主側にとっても、法人である家賃保証会社の利用を促進する大きな追い風となったのです。
家賃滞納時のリスクを確実にカバーでき、契約手続きもスムーズな保証会社の利用は、今後さらに賃貸業界のスタンダードになっていくと予測されます。
参考:法務省「賃貸借契約に関するルールの見直し」
保証人不要物件なら賃貸テックのビジネスモデル特許がおすすめ!
保証人不要の賃貸物件をお探しの方には、独自のビジネスモデル特許を持つ「賃貸テック」がおすすめです。
従来の賃貸契約とは一線を画すサービスで、入居者により多くのメリットを提供しています。
掛け捨てだった保証料が最大80%戻ってくる
賃貸テックでは、提携する家賃保証会社をご利用いただき、「良い住まい方」を実践してくださった方に、初回家賃保証料の最大80%を退去時にキャッシュバックしています。
「良い住まい方」とは、家賃を滞納することなく支払い、お部屋を丁寧に使っていただくなど、ごく当たり前のことです。真面目で誠実な暮らしぶりが、きちんと金銭的なメリットとして評価される。それが、賃貸テックだけの新しい賃貸契約の形です。
たとえば、初回家賃保証料として5万円をお支払いいただいた場合、退去時に4万円が返金されるため、実質の負担はわずか1万円。従来の「掛け捨て型」と比べても圧倒的にお得です。
管理会社と直接やり取り!仲介手数料が最大無料に
賃貸テックでは、管理会社と直接やり取りできるシステムを採用しています。専用マイページに希望する物件条件を登録しておくだけで、管理会社から直接オファーが届くのです。
このシステムにより、従来のように不動産会社を介さないため、賃貸契約時に大きな負担となる仲介手数料が最大無料になります。
物件に関する詳細な情報を得やすく、希望条件に合致した物件を効率的に見つけることが可能。さらに、契約条件についても気軽に問合せできる点も大きなメリットで、「家賃を少し下げてくれたら契約できる」「初期費用を削れないか」といった相談にも、スピーディーな回答が期待できます。
保証人不要に関するよくある質問

最後に、入居希望者から寄せられることの多い質問を整理しました。初めて保証人不要物件を探す方や、審査に不安を感じている方もぜひ参考にしてください。
Q:無職やフリーランスでも保証人なしで部屋を借りられますか?
A:無職やフリーランスの方でも保証人なしで賃貸物件を借りることは可能です。しかし、通常よりも審査が厳しくなる傾向があります。
無職の場合は、預貯金残高証明書が重要な審査材料となります。預貯金の残高が十分にあることを証明できれば、審査に通りやすくなるでしょう。また、次の就職先が決定している場合は、内定通知書などの提示が求められます。
フリーランスの場合は、確定申告書や取引先との契約書、直近数か月の通帳コピーなど、収入の安定性を示す資料を充実させることが大切です。
Q:UR賃貸住宅なら保証人も保証会社も不要って本当ですか?
A:はい、UR賃貸住宅では保証人も保証会社も不要で契約できます。
ただし、申込者本人に規定の収入基準を満たす必要があるなど、独自の審査基準が設けられています。
| 【UR賃貸住宅申込条件】収入基準:URが定める基準月収額以上の安定した収入があること 国籍・居住要件:日本国籍、またはURが認める資格を持つ外国籍の方で、ご自身が住むための住宅を必要としていること 同居要件:単身者、または同居する親族がいること 入居時期:入居可能日から1ヶ月以内に入居できること 反社会的勢力でないこと:申込者および同居者全員が暴力団員などではないこと |
参考:UR賃貸住宅「お申込み資格」
Q:緊急連絡先も頼める人がいない場合はどうすればいいですか?
A:緊急連絡先を頼める人がいない場合は以下の方法があります。
- 緊急連絡先代行サービスを利用する
- 自治体の福祉課に相談し、地域包括支援センターなどを紹介してもらう
- NPO法人や専門団体が提供するサポートを利用する など
このように、身寄りのない高齢者や単身赴任者でも安心して契約できる体制が整ってきています。
Q:緊急連絡先と連帯保証人は何が違うのですか?
A:緊急連絡先と連帯保証人では、その役割と法的な責任が全く異なります。一番の違いは、家賃の支払い義務があるかないかです。
緊急連絡先は、あくまで本人と連絡が取れない時に不動産会社や大家さんが状況を確認するための連絡先であり、家賃を支払う義務は一切ありません。
一方、連帯保証人は契約者である借主と同じ支払い義務を負うため、万が一の際は家賃の請求を受ける可能性があります。
Q:利用する家賃保証会社を自分で選ぶことは可能ですか?
A:入居者が家賃保証会社を自由に選ぶことは難しいケースが多いです。
多くの不動産会社や物件の管理会社は、提携している特定の家賃保証会社を利用する流れを組んでいます。保証会社によって審査の基準や保証料の金額が異なるため、貸主側が安心できる会社をあらかじめ指定しているのが一般的です。
ただし、もし自分の状況(過去にクレジットカードの支払いが遅れたことがあるなど)に不安がある場合は、正直に不動産会社の担当者へ相談してみましょう。事情を考慮し、別の保証会社を選択してくれる可能性があります。
まとめ
現在の賃貸市場では、家賃保証会社の普及により保証人なしでも物件を借りることが可能です。2020年4月1日の民法改正を契機として、保証人制度から保証会社利用への転換が加速し、現在では賃貸契約の約80%で保証会社が利用されています。
家賃保証会社市場は今後も成長が続く見通しで、サービス内容もより多様化していくと予想されます。保証人不要の仕組みを正しく理解し、自分の状況に最適な選択肢を見つけることで、納得のいくお部屋探しを実現できるでしょう。
賃貸テックでは、真面目な入居者が損をしない「保証料キャッシュバック」という独自のサービスを提供しています。保証人不要のお部屋探しで、金銭的な負担を少しでも軽くしたい方は、ぜひ賃貸テックのサービスを利用してみてください。