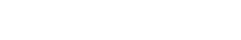賃貸物件の保証料とは? 料金を安くおさえる方法を解説!
- 2025.07.12
- 家賃保証料

賃貸物件の物件概要や募集要項を見ていると、「家賃保証料」「賃貸保証料」「保証更新料」「月額保証料」など、さまざまな呼び方で保証に関する費用が記載されていることがあります。これらの名称は一見バラバラに見えますが、基本的にはすべて「家賃保証会社のサービスに対して支払う費用」を指しています。この保証料が何か分からない方も多いのではないでしょうか。ここでは、保証の役割や保証料の目安について解説していきます。
家賃の保証契約って何?
家賃保証契約とは家を借りる際や店舗・駐車場等さまざまな賃貸借契約時に、借主と家賃保証会社の間で結ばれる契約で、この契約期間に家賃(及び管理費)を滞納した場合、家賃保証会社が借主に代わり、貸主(大家さん・オーナー)に賃料を一時的に立て替えるサービスです。借主は後日、家賃保証会社からの請求に応じて滞納分を返済する流れになります。
過去の賃貸借契約では貸主や管理会社(不動産会社)から、事前に家族や親族に「連帯保証人」の役割を求めましたが、最近は家賃保証契約を結ぶことを必須とするプランが増えてきました。
家賃保証契約時に初期保証料が発生します。初期保証料は一般的に保証会社や家賃等によって異なります。家賃が高額な場合保証料も高くなります。契約時に家賃の半額から1か月分程度を支払い、その後、1年ごとに継続保証料が1万円程度発生するケースが多いようです。また継続保証料を毎月払う、支払い方法が異なるサービスを提供している保証会社もあるようです。費用の支払い時期や徴収方法によって「賃貸保証料」「家賃保証料」「初期保証料」「保証更新料」「月額保証料」など、呼び名が変わります。また、保証の内容及び条件は保証会社により異なります。
そうとはいえ、必ず家賃保証契約を利用できるわけではありません。申込時に保証会社の審査があります。
家賃保証契約は、賃貸経営を営む不動産の貸主にとってもメリットのある仕組みです。借主が家賃を滞納しても、保証会社がいったん借主に代わり立替えて対応してくれるため、安定した賃貸収入を確保できます。
家賃保証契約には貸主と借主、それぞれにとってメリットがあります。
保証契約を利用するメリット(理由)
保証人を頼める親族がいない場合や、頼みにくい状況で役立ち、家賃保証に加入することにより、部屋を借りやすくなります。
保証人を探す手間や、保証人が立てられないことによる契約不成立のリスクがなくなるため、物件契約時のストレスを軽減できます。家賃保証契約は通常、家賃を保証するだけでなく、契約に関連した手続きをスムーズに進めることができるため、借主となる者にとって非常に便利でおすすめです。
近年では、賃貸借契約時に家賃保証契約を締結する事が一般化し、連帯保証人を不要とするケースも増えてきているようです。
審査が簡単でスムーズ
連帯保証人を立てる場合、借主及び連帯保証人の信用調査が必要となり、場合によっては時間がかかることがあります。一方、家賃保証契約なら、借主のみの審査となるため、全体的に手続きが少なくなりスムーズです。
家賃トラブルの対策
借主が入居した後、万が一家賃を滞納した場合でも、保証会社が一時的に家賃を立て替えます。このため、貸主は家賃等、管理の不安を取り除く意味で安心頂けます。
保証契約を利用するデメリット
借主側にとって、家賃保証契約のデメリットも存在します。
保証料が発生する
家賃保証契約後、保証料の支払いが求められます。保証料は家賃の一定割合(通常は1ヶ月分〜数ヶ月分)が多く、長期的に見るとコストがかさむ可能性があります。この料金は借主負担となるため、賃貸契約にかかる総費用が増えることになります。
審査がある

賃貸契約を結ぶ際、多くのケースで「賃貸保証会社」の審査を受けることが必要になります。審査基準を満たさない場合、契約が締結できないことがあります。収入や信用情報によっては、保証契約が成立せず、物件探しが難しい状況となる場合があります。これは、家賃の滞納が発生した場合でも貸主が安心できる仕組みであり、入居者にとってもお部屋を借りやすくする大きな機能を果たしています。そのため、審査に通るかどうかが契約全体に直結する重要なポイントとなります。
まず審査に必要な書類として、身分証明書や収入証明書が基本となり、場合によっては勤務先の在籍確認や保証人に関する情報も求められます。種類は保証会社ごとに異なりますが、上記のような内容をしっかり用意しておけば、スムーズに進めてもらえる可能性が高まります。加え、直近1年の収入を確認される傾向が強く、安定した収入があることが審査の基準として有効に働きます。もし自分の収入が少ない場合は、同じオフィスに勤務する家族の収入を併せて提出できるシステムがある会社も存在します。
審査は基本的に数日で行われ、結果が出るまでの期間は1〜3日前後が一般的です。ただしタイミングによっては、物件への申し込みが重なることもあり、希望する部屋を他の方に先に契約されてしまう事例もあります。したがって、気に入ったお部屋が見つかったら、サイトに掲載されている必要書類の詳細を確認し、すぐに行動を行うことをオススメします。
なお、審査に落ちる原因は「支払能力が不十分」「過去に家賃滞納の履歴がある」などが主ですが、これ以外にも携帯電話・クレジットカード・各種ローン等の支払い遅延が含まれている場合があります。もし不安があれば、不動産会社に直接相談しましょう。
また、契約更新の際にも保証会社への更新料を支払わなければならないケースが多く、1年ごとに費用が発生することがあります。これは義務として定められているため、「安い保証会社を選択したい」と考える方は、初回契約時に方針を確認しておくと良いでしょう。
一方で、保証契約だけを解約することは原則できません。契約自体を終了させたい場合は、賃貸契約の解約と同じタイミングで行い、原状回復費用を含めた清算を行う必要があります。
このように、賃貸保証会社の審査に関わる問題を避けるためには事前に適切な準備が欠かせません。上記の内容を理解しておけば、自身のお部屋探しにおいても安心して進められるでしょう。現在はインターネットで詳細を簡単にご覧いただける環境が整っており、必要書類を事前に確認するだけでも審査通過の確率は大きく上がります。ぜひ余裕を持った準備を心がけましょう。
滞納時に代位弁済手数料が発生する
借主が家賃を滞納した場合、保証会社が一旦家賃を立て替えるサポートがありますが、その後、保証会社から借主に対して滞納分の回収の他、代位弁済手数料が発生します。
代位弁済手数料は、家賃を立て替えたことに対する保証会社への手数料です。
家賃滞納が繰り返されると、代位弁済手数料が累積して高い負担となる可能性があるため、滞納を防ぐよう心がけることが重要です。また、滞納を繰り返すと契約継続時に払う継続保証料が今まで以上に値上げされるケースもあるので注意しましょう。
保証料の料金体系を解説
保証料の料金体系
保証料は一般的に契約時の初回に支払う「初期保証料」と、その後継続的に支払う「継続保証料」の料金体系で構成されています。
保証料の相場ってどれくらい?
家賃保証契約利用の際、借主は保証会社に初期保証料の支払いが求められます。この初期保証料の額は物件の家賃の金額に基づいて計算されることが一般的です。初期保証料の仕組みは、家賃の一定の割合(例えば50%〜100%)を支払う形式となっており、契約時に必ず確認・チェックしておくべきポイントです。
家賃保証契約が継続される場合、継続保証料が求められます。継続保証料は、家賃の数%(契約体系によって10%〜30%程度)の料金設定が多いようです。継続保証料の支払い方法には、年払い・月払いがあり、近年月払いが一般的になっているようです。
必ず保証料を払わないといけないの?
賃貸物件を内見した後、賃貸借契約を進めるにあたり、家賃保証契約と初期保証料の支払いが求められます。また家賃保証の契約更新は、おおよそ1〜2年周期ごとに行われ、保証更新料の支払いが求められます。
注意点として、この保証料(初期保証料・保証更新料)が支払えない場合、保証会社から督促され、自宅、職場、緊急連絡先等に連絡が行くこともあります。場合によっては、強制的に解約・退去となってしまう点があります。
最悪、保証会社のブラックリストの一覧に個人情報が掲載され審査が通りづらくなります。その影響により選べる物件(住宅)が限定され、引越しが難しくなります。また、クレジットカードやローンの審査も通りにくくなる恐れもあります。遅れずに支払うことが大切です。
保証料を安く抑えるには?
保証会社によって保証料は異なります。初回保証料、更新料、月額保証料などの項目を比較し、最もコストがやすく抑えられる保証会社を選びましょう。
マンションやアパート等、募集されている物件によっては管理会社や貸主から予め保証会社が指定されている場合もございますが、借主に有利な保証会社の紹介が可能か交渉し、選ぶように対策すると良いでしょう。
保証料は戻ってくるの?
賃貸契約時に支払う家賃保証料は、基本的に戻ってくるお金ではありません。これは、家賃保証会社が借主の家賃滞納時に立て替えを行う「保証機能」の対価であり、サービス提供の期間に対して支払う料金だからです。そのため、契約途中で退去しても、未使用分を返金してもらえない事例が大半です。
例外として、契約開始前にキャンセルした場合や契約自体が成立しなかった場合は返金されることがあります。ただし、種類や契約条件によって対応は異なり、詳細は契約書や約款をしっかり確認する必要があります。特に「初回保証料」や「継続保証料」など、料金体系ごとに扱いが違うため、自分の契約内容を理解しておくことが重要です。
保証料は敷金や原状回復費用と異なり、退去後に返金される性質のものではありません。条件を理解したうえで契約することが大切です。
初期保証料について
賃貸契約時に支払う初期家賃保証料は、初期費用の中でも大きな割合を占めます。少しでも安い金額に抑えるためには、事前の情報収集と交渉が重要です。まず、保証料の計算方法や型(年払い・月払いなど)の違いについて知識を持つことが第一歩です。これらは契約書や保証会社の詳細ページでご覧いただけます。
次に、同じ家賃でも保証会社によって金額が異なる事例があります。物件を探す際は、家賃や立地以外にも「どの保証会社を利用しているか」を確認し、希望に合う条件を選ぶのが有効です。複数の賃貸ポータルサイトを比較し、保証料が安い物件を選択肢に含ませましょう。
交渉のタイミングも重要です。契約前後の時期に、仲介会社へ「別の保証会社を利用できないか」や「保証料の値引きが可能か」を相談してみてください。適切な条件で調整してもらうことができる場合もあります。
注意点として、保証会社は契約満了まで変更出来ない事が一般的なため、契約前に方針を固め、条件を比較したうえでお部屋を選ぶことが大切です。初期保証料を抑えるための対処法は限られていますが、準備と交渉次第で負担を軽減することは可能です。
継続保証料について
「継続保証料」は、保証を継続するために支払う料金です。支払い方法は毎月払い・年払い等があり、保証会社やプランにより異なり、賃貸借契約が続く限り支払う義務があります。現在ほとんどの物件で採用されています。
保証契約開始後に保証会社の変更は出来ませんので、賃貸物件にどの保証会社のプランが適用されるかを事前に確認し、負担が少ない物件を選ぶ事が大切になります。
まとめ
一般的に売買と違い、賃貸借契約における諸費用は、仲介手数料・敷金・礼金・初期家賃保証料・火災保険料等があります。大手ポータルサイトに登録されている人気物件や、気になるエリアの物件でも、賃貸テックを通じて賢く契約すれば、仲介手数料が最大無料(0円)はもちろん、初期家賃保証料が退去時に最大80%キャッシュバックされる等、節約思考向けの特徴があります。これらのことから、賃貸テックを活用すると初期費用のお金を節約でき、入居者の利益にも繋がりおすすめです。収入や予算、暮らしにあった複数のサービスと比較・検討頂き、ぜひキャッシュバックキャンペーン付き家賃保証契約を提供している賃貸テックに安心して気軽にご相談下さい。